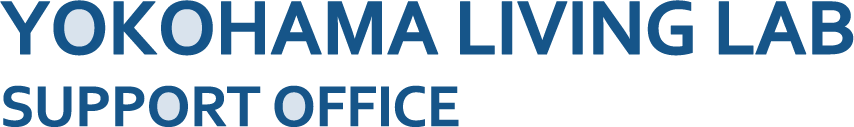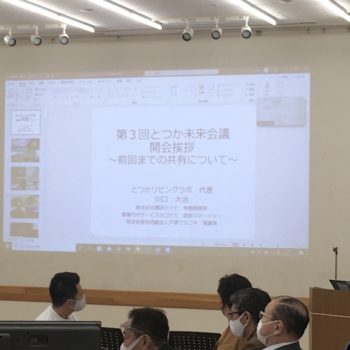World Living Lab Day 4-2:ヘルスプロモーション~ウェルビーイングを実現するリビングラボ~【イベントレポート】
- On 2021年2月10日
2020年11月2日(月)〜8日(日)に開催された「World Living Lab~レジリエントで持続可能な都市・横浜を目指して~対話とワークショップでポストコロナの循環型経済を切り開く7日間~」。今回のワールドリビングラボでは、「サーキュラーエコノミーplus」の4つの活動領域に沿って、新型コロナウィルスがもたらした社会課題に対する新たなソリューション創出や、様々な危機に対する大都市のレジリエンスを高めていくため、横浜市内各地のリビングラボが基軸となり、7日間にわたり8つの国際的な対話のプログラムを開催しました。
本記事では、4日目の2020年11月5日に開催された「DAY4-2 ヘルスプロモーション:ウェルビーイングを実現するリビングラボ」のレポートをお届けします。市民が健康でいきいき暮らし続け、身体的・精神的・社会的に幸福であり続ける社会を実現する~超高齢・人口減少社会を救う医療・福祉のオープンイノベーションについてお話する様子をレポートします。
今回のフューチャーセッションでは、21世紀の成長産業であり、超高齢・人口減少社会の諸課題を解決する鍵を握ると言われる生活サービス産業のイノベーションを図るという観点から、医療・介護・ヘルスケア・スポーツをシームレスに結び付け、市民一人ひとりのウエルビーイングを達成するための方策を探ります。
まず初めに、加藤 佑さん(ハーチ株式会社 代表取締役)の基調講演です。
加藤 佑さん(ハーチ株式会社 代表取締役)

「サーキュラーエコノミー(循環経済)は世界中で注目されており、国内も環境省では地域循環共生圏としてその概念の取り組みを推進しています。サーキュラーエコノミーは有限である地球資源を循環していくという環境的な側面に経済の視点がはいっているため、環境的な側面と経済的な側面を中心に語っています。2020年には欧州でサーキュラーエコノミーパッケージが発表され、アフターコロナで循環経済を加速させていく動きが世界では見られます。」
また、新型コロナウイルスで影響を受けた経済をどのように回復していくのかを考えるために『グリーンリカバリー』という環境負荷が少ない経済活動の復活議論されています。
「いままでは地球(環境)と利益(経済)に焦点が置かれていましたが、やはり循環型経済へ移行する主体は『人』なので、社会的な側面も考えて循環型経済だけではなく、循環型『社会』の概念に拡張し、『ドーナツ経済学』という概念も出てきています。」
つまり、環境負荷を抑えつつ地球上に暮らす人々にも公平に資源を分け合っていく必要性が認識されているのです。
「そして、循環型経済を遂行する意義を考えたときに、今回の主題にある『ウェルビーイング』が目的になるのではないかと考えています。『ウェルビーイング』は日本語では『長期的な幸福』という意味を指しています。また、世界には『ウェルビーイングエコノミー』ということばがあり、特に循環型経済に先進的に取り組んでいるスコットランドやニュージーランドなどの国は『ウェルビーイングエコノミー』を中心とする経済活動を推進しています。このようなことから、循環型経済に目的を与えるためにウェルビーイングは存在しているのではないかと考えています。」
ウェルビーイングに横浜独自の『サーキュラーエコノミープラス』を紐づけると、あらゆる作り手を増やしていくために、あらゆる人が経済に参画するプロセスを通じて地産地消のモデルやヘルスプロモーションにつながり、地域循環が作られ、人々の生きがいになるのではないかと加藤さんは続けました。
「ウェルビーイングは環境、社会、経済の3つの要素があります。どんなに自然が豊かなところに住んでいても人とのつながりを持ち、社会的活動に参画していることがとても重要です。それを実現するために経済的土台が必要であり、経済活動が継続できると環境も保護され、社会も豊かになる必要があります。これら3つをすべて満たして、初めてウェルビーイングを実現できると考えるとサーキュラーエコノミープラスのなかにウェルビーイングが入っていることにとても意味があると感じています。」
横山太郎 YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス ヘルスケア部会長

横山さんは、医師から与えられた選択肢のなかから患者が自信をもって治療法を選べるような環境の実現に向け、日々医療に従事しています。
「特に慢性疾患は入院しても治らず、治療が生活スタイルに影響します。しかし生活様式は、医療者だけで支えるのは厳しいため、市民が医療に関わることが求められています。実際に、病棟のボランティアが患者さんと関係を構築し、気持ちを聞いてくれるような役割を果たしている事例があります。他にも、治療医以外の医療者がかかわると、患者さんのウェルビーイングが上がり、寿命が延びるという論文結果があり、これらのようなことを日本でも実現したいと考えています。」
医療はいままで専門家だけが担ってきましたが、医療の質や経済的な理由から、市民とコラボレーションすることが大切だと横山さんは強調しました。
「アメリカのアラバマでは、住民ががん患者の診療に付き添うケースがあります。結果として市民は医者から知識を得ることができ、患者の満足度が上がり、緊急入院が下がり、全体的に医療費が下がったという結果が出ています。そしてその浮いたコストは支援している市民に給与として支払われるので、関係者全員にとってwin-winな取り組みと言えます。」
一方日本ではこのような取り組みがあるのかを考えてみると、まだまだ少ないのが現状です。しかし、きっかけさえあれば参加してくれる人もいると考え、横山さんはきっかけづくりとして私立公民館設立にも尽力しています。
「アメリカでの視察を経て試行錯誤した結果、アメリカの成功事例は必ずしも日本に当てはまるわけではないと考えました。日本では、まず初めに動画をつかって知識を得てもらう教育の取り組みを始めています。実際には、普段医療現場で患者へ説明している癌が発生する仕組みを映し手編集し、動画を制作しています。この動画を見ると患者さんが今までのように口頭で説明しているときよりも理解してくれ、具体的な質問や相談をしてくれるようになりました。」
今後も、医療と介護がつながりやすい場所である竹山病院で、活動を応援したい住人と共にこの取り組みを進めています。
「リビングラボサポートオフィスでは『市民の生活を看る医学部』を作ります。医学部では、医療のIT化を推進し、患者が入院するのと同時に自宅に戻った際に遠隔診療ができるようなIT教育を治療と同時に施します。コールセンターも作り、患者から来た相談や質問をデータ化し、だれでも質問に答えるようになるような仕組みも作っています。」
現在はコミュニティナースを中心に、まずは学生と一緒に始めていきたいと話す横山さん。興味がある方は、ぜひ登録をしてみてください。
横山さんのお話を聞き、加藤さんが自走することの重要性をコメントしました。
「自分たちで作れるようにすることがサーキュラーエコノミーを実装するなかで重要です。自分たちができることから始め、地域が分散して個人が担い手になることで地域循環のインフラの構築につながると思います。そのためにはテクノロジー(ICT)の力に頼ることは大切で、便利さを追求し、効率をさげずに仕組みづくりをすることでレジリエンスを高めることができるのではないでしょうか。」
お二人の話を聞き、太陽住建の河原さんから感想を述べていただきました。

「サーキュラーエコノミープラスはそれぞれの概念が繋がっていると改めて感じました。我々が活動している、高齢者のオンライン講座も地域から上がってきたアイデアです。知人との交流が少なくなると認知症が促進していくため、コミュニティ不足が課題に上がってきます。ヘルスプロモーションの側面で課題を解決すると必然的にほかの領域の課題も同時に解決することにつながっていきます。サポートオフィスはそれらのオープンイノベーションのハブになると感じました。」
横浜市政策局共創推進室の関口さんも、個性や能力に合わせた働き方を地域に創っていくと地域が活性化されると同意しました。協働診療所が障害をもっている方に働く場所を提供すると、医療が協働する場所になり、新しい働き手を作ることがとても重要になると話しました。
緑園リビングラボの代表を務めている野村さんから、持続的可能な働き方に関して意見をいただきました。

「私の職場は、母親が中心の職場です。母親たちが家庭を大事にしながらも働こうとおもうと持続可能な働き方につながっると感じているため、働き方や参加の仕方をを工夫することでいろんな人と一緒に活動ができます。そして様々な背景や特技、知識、想いを持った人が参画すること自体が持続可能だと思っています。」
野村さんは、お母さんが中心の職場でお母さんたちの働きやすさを考え日々活動し、「学ぶ」「働く」「暮らす」が近い場所でできるエコシステムを創っています。緑園リビングラボの取り組みはこちらの記事から。
リビングラボサポートオフィス理事、税理士法人エンパワージャパン代表で中小企業の財務支援をしている穂坂さんからも感想をいただきました。

「新型コロナウイルスによって、これからの企業の在り方を考えさせられるようになりました。企業が存続するには、商品やサービスを提供するだけではなく、別の存在意義や存在価値が必要になり、結果的にウェルビーイングが重要になってくるのではないでしょうか。企業の存在目的の一つは、雇用を創出することです。従業員も地域で生活を担う一員であり、彼らの永続的な幸せを担っていくのは企業で、企業が個人を支援することが循環型社会のカギになっていると考えます。」
市民活動と企業活動を切り離すのではなく、お互いに共存する取り組みを意識することで循環ができると話しました。
また、子供たちが地域を担う人材として活躍してく社会を作るために、穂坂さんは児童養護施設で虐待や育児放棄にあった子供たちが地域で活躍するためのキャリア形成や教育、地域の企業に就職するまでの支援活動をしています。
船山大器さん(一般社団法人YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス 再エネ部会)からも感じたことを共有していただきました。

「お話を聞いていると、医療と私が携わっている再生可能エネルギーは近しいと思いました。一般市民にとって、遠いけど近い世界ですね。数十年前は、提供者と消費者が一緒になって、電気を売ることと買うことが一緒になることなんてできないと笑われていたが、今は実現しています。このように、想いがあって、実際に動いていて、地域で活動していれば必ず実現できると私は信じています。私も仲間として想いをどんどん伝えていきたいし、一人ではできないことを仲間として広げていきたいです。」
中島翔さん(磯子・屏風ヶ浦のトータルビューティサロン 株式会社TRIPLE-ef 代表取締役)からも意見をいただきました。
「美容室は地域を作り上げる仲間が定期的に対話し、地域の情報をもらう空間です。リビングラボに加わることで地域の意見や人の困りごとを循環して届ける仕組みができました。このように、人が集まる場としてのハブとなれるような意識を持っています。日ごろのコミュニケーションを通じてウェルビーイングにつながるよう日々取り組んでいきたいと感じました。」
最後に加藤さんから一言いただきました。
「お話を聞くなかで、地域企業の役割は変わっていくと感じました。企業で働くことでウェルビーイングが実現でき、企業が課題を解決する主体となる姿勢が、これから求められる企業の姿だと考えています。また、サーキュラーエコノミー実践のポイントは多様性です。だれかにとっての無駄が他の人にとっての資産になります。多様性が担保され、つながりをつくるプレイヤーがハブとなって循環を作っていき、コラボレーションを生み出していくのではないでしょうか。」
横山さんからも最後に締めの言葉をいただきました。
「活動を始めても結果が出ないとやめたくなるのですが、20年はがんばろうと思いました。今までは誰かしらが描いた絵のパズルを埋めるような感覚で活動していましたが、レゴに近くなってきたのではないでしょうか。レゴであればひとつのパーツがなくなってきても成り立つので、個の時代が主体になります。企業にも社会的責任があるのであれば、その企業で働く個も社会的責任を果たす必要があるのではないでしょうか。そのため、横浜のなかでもどのような大きさの企業とも協働していき、ハブとして機能することで大きな動きができていくと思います。そのためには、個人のレスポンシビリティがキーになると思いました。」

取材後記
欧州で提唱されているサーキュラーエコノミーは「経済」と「環境」の視点が入っていますが、そこに「社会(人)」の視点を加えられた横浜独自の「サーキュラーエコノミープラス」は、まさに人が長期的に幸せに暮らせるための「ウェルビーイング」を実現することができると対談を通じて改めて認識することができました。
あらゆる分野や団体が共創してこそ作り上げられる循環型社会では、個人の多様性が重要になります。新型コロナウイルスを発端に人々の働き方やライフスタイルは少しずつ変化しています。居住や仕事をする場所や複業の推進など、パラレルキャリア人財の増加が予想されます。個人がダイバーシティに富むことで地域が豊かになり、循環型社会に貢献できるのではないでしょうか。