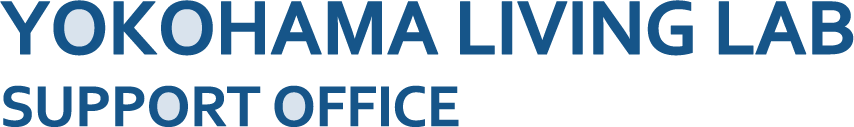「とつかリビングラボ」によるコロナ危機への対応
- On 2020年5月1日
- こまちぷらす, ツクイ, とつかリビングラボ, リビングラボ, 戸塚, 戸塚区, 戸塚宿ほのぼの商和会, 戸塚旭町通商店会, 旭町通り商店会
戸塚区内の商店街でも新型コロナの感染拡大によって、各個店の売り上げが激減するなど大きな影響が出ています。こうした新型コロナがもたらした社会経済的な危機に対する商店街としての取組を「とつかリビングラボ」のメンバーで、JR戸塚駅前に店舗を持つ仁天堂薬局の代表取締役の湯川仁さんにお話をお聞きしました。
湯川さんは戸塚駅西口に広がる「戸塚旭町通商店会」(以下、旭町通商店会)の理事長も務めています。また戸塚区の商店会連合会の副会長も兼ねており、それだけに戸塚区内の商店街が力を併せて、新型コロナによってもたらされた危機を乗り越えて行こうという強い思いが言葉の端々に感じられます。
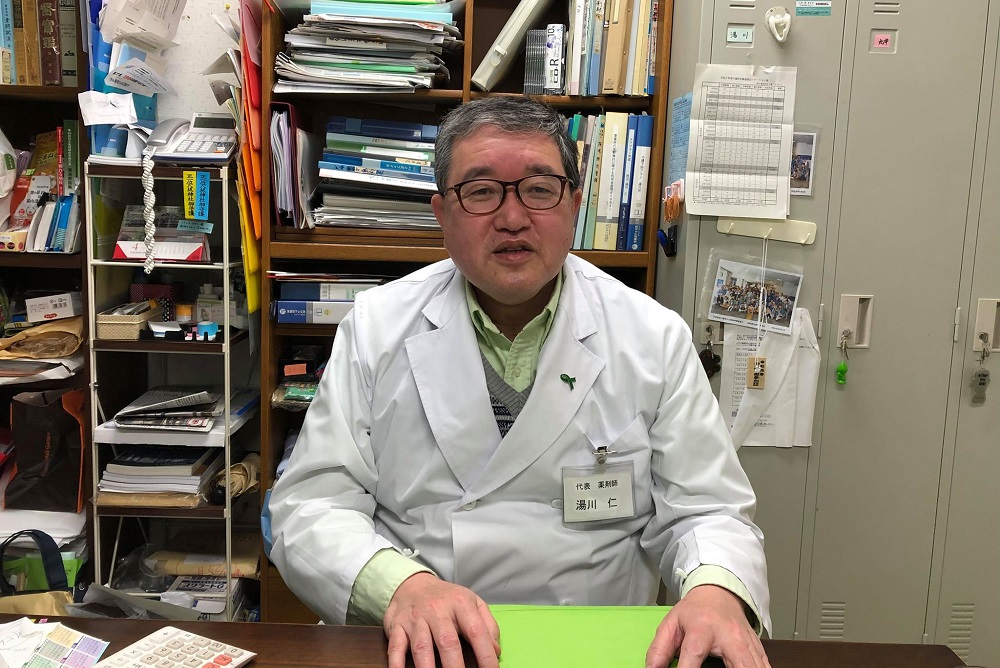
仁天堂薬局代表取締役・湯川仁さん
湯川さんが商店街のコロナウィルス感染対策として第一義に進めるのは、お客さんが安心して来店できる衛生環境づくり。いわば、各お店の従業員が徹底的にマスクをし、消毒液を配備するなど感染防止と商売を両立させるためのソフトインフラづくりです。そのため、戸塚区商店会連合会として、横浜市の助成制度を積極的に活用し、区内の各商店街でアルコール消毒液やマスクなどの衛生用品を積極的に調達しようとしています。

戸塚旭町通商店街の街並み
ところが、マスクも消毒液も、もともと消耗品であるばかりでなく世界的に在庫薄になっているため、十分な量が確保できないと湯川さんは、言います。そこで湯川さんは、薬局ならではのネットワークを活用してマスクを購入し、旭町通商店会の各店舗のみならず、薬剤師として往診訪問をしている在宅療養者や県立こども医療センターなどに無償で配ることを企画していると言います。まさに困った時には「おたがいハマ」の精神ですね。
今一つ、今回の非常事態宣言をきっかけに旭町通商店会で始まったのは、「夜回り」です。商店会の各店舗が夜間に営業自粛をするようになり、同時に地区センターや公会堂などの公共施設が閉館される。それで戸塚駅周辺の夜が以前と比べて格段に暗くなった。夜道を歩いていたら痴漢に遭ったという話も聞く。それで街の防犯活動の一環として、商店会の有志で夜間パトロールを始めたそうです。

夜回りの様子
ただ、通常はこういう地域の防犯パトロールは、集団で行うものなのですが、コロナの感染拡大防止のため、商店主が一人、二人でも空いている時間に夜の街を廻ることにしています。こうしたパトロールの途上で、川の土手や暗がりに集まっている若者を見かけます。未成年も多くステイホームを促します。
小中高校が長期間休校になり、地区センターや図書館など公共施設やファーストフードのお店など街の居場所も閉鎖されています。しかも友人と直接会うことも自粛するよう社会から要請されている若者たち。自宅で大人しくSTAYしろと言われても、仮に家庭に自分の居場所がないとしたら、とてもストレスフルな状況にあるのではないかと思います。
湯川さんは、こういう子どもや若者も含めて、このコロナ危機による非常事態宣言をきっかけに、商店街が地域での経済活動やまちづくりの取組を通じて、あらゆる世代をつなぐコミュニティの場となるよう活動を広げて行きたいと言います。
旭町通商店会に隣接して、戸塚小学校を中心とした、柏尾川と国道1号線に挟まれたエリアに点在する商店で組織されている「戸塚宿ほのぼの商和会」(以下、商和会)でもコロナ危機に向き合う取組が始まっています。
「とつかリビングラボ」のメンバーであり、商和会の事務局を務める認定NPO法人こまちぷらす代表の森祐美子さんは、非常事態宣言による営業自粛が商店街の各店舗にどのような影響を及ぼしているのかを商店会として電話で一軒一軒、ヒアリングしたと言います。すると半分の業種は売上げを落としており、売り上げが9割減になった飲食店もあることが判明。

戸塚宿ほのぼの商和会の街並み
「これは何とかしなければ」と商和会のメンバーで、ケアプラザの生活支援コーディネーターや子育て支援拠点の職員、主任児童委員や戸塚区役所の職員などにも呼びかけて、会合を開きました。そこで現状の課題を高齢者や子育て層や障がいのある方について聞き、出されたアイデアは、外出自粛で自宅に籠る一人暮らしの高齢者に商和会として宅配サービスを行えないかというもの。コロナ危機によって社会的孤立の度合いを深める単身高齢者と経営が厳しい状態にある飲食店とをマッチングすることで、両者が抱える課題を解決しようというアイデアです。

認定NPO法人こまちぷらす代表・森祐美子さん
しかし、個別の家への宅配は個人情報の問題もあるし、そもそも商和会に所属する飲食店はオーナー店長が家族とやっているケースなど、ギリギリの人数でお店を廻しており、宅配するだけの人的な余裕がないお店がほとんど。そこで森さんは、「とつかリビングラボ」の仲間に相談したと言います。
特に横浜で生まれ育った地元の大手の介護事業者である㈱ツクイの菊池友香さんには、「ツクイの訪問介護利用客向けに、商和会に所属する飲食店から昼食等を提供する宅配サービスを実施できないか」と具体的に提案したと言います。ツクイの訪問介護職員がツクイの事業所に届けられたお弁当を持ってお客様宅に向かえば、訪問介護職員が宅配員の役割も兼ねられ、各店舗から配達員を出さなくても大丈夫なのではという発想からです。
ところが、実際には訪問介護の職員は、事業所には寄らず、自宅から直接利用者宅に向かうため、商店街の飲食店から宅配用の料理を受け取るタイミングが難しく、この提案のスキームのままでは、実現は難しかったと菊地さんは言います。
そこで菊地さんは、㈱ツクイが運営している通所介護事業所やサービス付き高齢者住宅(以下、サ高住)の利用者に対して、商和会に所属する店舗から宅配サービスを提供する案はどうかと、森さんに逆提案します。これならば、費用対効果が高く、現実性があるからです。
そして、この逆提案に基づいて、㈱ツクイのメンバーと商和会の役員とが話し合った結果、商和会から5店舗が参画する形で、5月中旬からまずは通所介護事業所(戸塚区3か所)とサ高住(戸塚区2か所)で試験的に実施することになりました。

ツクイ横浜戸塚川上
実施にあたっては、サ高住の入居者に㈱ツクイが注文を取り希望者へ提供、また通所介護事業所では、当日の全利用者を対象に昼食を提供することにしました。昼食の提供は各店舗から各施設に直接配送する形を検討しています。他、現在タクシー業界も厳しい状況にあることから、タクシー会社による宅配等も今検討しているようです。
㈱ツクイのメンバーは、この配食サービスの取組を試行的に実施しながら、施設利用者ごとに味、量、価格などの観点からメニューを調査・調整していく必要があると言います。例えば、通所介護利用者に対して濃い味のメニューを提供することは好ましくなく、高価格のメニューは好まれない。一方で、サ高住利用者は味の制限は少なく、価格は高くてもこだわりのあるメニューの方が好まれるのではないかなど、各施設利用者のニーズと各店舗が提供できるメニューとをマッチングさせたうえで提供をしていきたいそうです。
森さんも菊地さんもこの試みが上手く行ったら、小規模多機能や有料老人ホームなど他の施設の利用者へも横展開して行きたいと言います。それによって、この取組をコロナ危機に対する一過性のイベントではなく、アフターコロナを想定した持続可能なビジネスにすることができるからです。
コロナ危機を乗り越える新たなサービスの創出は、誰かが、誰かを一方的に支援するボランティアではなく、金銭的にも両者がウィンウィンの関係になることが求められるのではないかということを考えさせられる「とつかリビングラボ」らしい取組だと思いました。
「とつかリビングラボ」による、この商店街と介護事業者が結びついた配食サービスの事業実践については、引き続き取材し、検証して行きたいと思います。(関口・有馬)
【参照ページ】とつかリビングラボ